
浅口市は、平成18年3月21日を持って、浅口郡(金光・鴨方・寄島)が対等合併してつくられた玉島の西隣の市である。
浅口の名が歴史上に最初に表れるのは、『続日本記』という国史の書物のである。それから同じく、『和名抄(わみょうしょう)』という平安時代の書物には、諸国の郡郷名が記録されており、その中に、浅口郡八郷といって、阿知・間人(まむと)・船穂・占見(うらみ)・川村・小坂(おさか)・林・大島の八つの郷名が載せられている。
この事より、平安時代頃には、浅口という名があったということであろう。
この頃、現在の玉島新町通りから羽黒山を経て、土手町に至る筋は、大小の岩が点々と連なった瀬戸で、干潮時や満潮時には潮が大渦を巻いて急流であった。これにより、土砂も自然と押し流されて、水深は深くなり、大型の船にとっては通りやすい場所であったが、急流であるために難所であった。
そのため、小型の船舶などは、瀬戸内の大海を避け、甕の泊付近を航海した。この周辺は、高梁川から土砂が流れ込み、それほど深い海ではなかった。
この事は船乗りの間で、『甕の泊に入るためには、出入口の浅いところを通らねばならん』と言い伝えられ、ここがいつしか『浅口』とよばれるようになったと思われる。現在の浅口市付近でつけられた名前ではなく、現在の富田付近より発祥した名であると思われる(この時代の行政区分では富田も浅口郡であった)
今回の合併によりこの名が消えなかったことは胸をなでおろす気分である。

西暦200年頃、仲哀天皇の妻であった神功皇后は、朝鮮新羅へと遠征するために、難波の港(現在の大阪府)から出航し、瀬戸内海を航海して新羅に向かったと言い伝えられる。この遠征の帰路、現浅口市寄島町の沖合いの小島に立ち寄られたといわれる。この事より、神功皇后が寄った島 ⇒ 寄島 となった。そして、この島の西南に続く『三ッ山』で神功皇后自ら天神地祇を祀り、戦勝を感謝された。その時、神勅があり、『三郎島』と称するようになったともいう。
確かに、三郎島には、神功皇后、神功皇后の夫である仲哀天皇・応神天皇(仲哀天皇と神功皇后の息子)の三神をそれぞれ祀っているといい、この話もうなづける。

浅口市の東部に位置する金光町。
ここは、金光教本部が置かれる町として、縁日には多くの信者が集まる。
この金光教の教祖は、金光大神であり、この神の名から自然とこの町が金光と呼ばれるようになったのではなかろうか。

地頭とは、平安末期、所領を中央の権門勢家に寄進し、在地にあって荘園管理に当たった荘官・、鎌倉時代全国の荘園・公領に置かれ、土地の管理、租税の徴収、検断などの権限を持った役職・江戸時代、知行取りの旗本で各藩で知行地を与えられ、租税徴収の権を持っていた家臣をさす、これらのどれかがこの地に居たことよりこの名がついたと思われる。

調査中

益坂は、鴨方町の北東部に位置する。
ここは、遥照山のふもとであり、山際に隣接する地区である。このことから、しだいに山々の傾斜が増していく地形がそのまま地名に転移したのではないかと推測してみる。
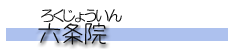
平清盛の父 忠盛がこの地を、白河法皇ゆかりの京都の六条院に寄進したことより由来となった。
以下続々追加!の予定。
