

柏島は、乙島と海峡を挟んで西側に位置するが、源平の争乱『源平水島合戦』の際にも平家か源氏かどちらかの勢が陣地を取っていた場所である。ここもかつて孤立した島であった。
良寛で知られる円通寺の参道脇には、『本覚寺』といわれるお寺があり、昔一本の『柏』の霊木があったという。この寺の始まりから、柏島の由来を知ることが出来る。9世紀初め、当時大陸で勢力を誇っていた唐へ渡る途中この島の沖に泊まった慈覚大師(円仁)は、海上を光を放って飛ぶものを見たという。不思議に思った慈覚大師が、光を追っていった。すると、十一面観音が『本覚寺』にあった柏の古木に入り隠れたと言い伝えられる。これらの出来事により、柏島と名がついた。
これを見た大師は、その柏の木で十一面観音を作り、祀ったと言う。
また、玉島阿賀崎の由来は、慈覚大師がこの十一面観音に供える水(阿迦)を汲んだ跡を阿迦崎⇒阿賀崎となったとも言われる。

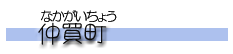
仲買町は、柏島の東ふもとに位置し、港に面している。ここにも新町同様、古い問屋や商店のあとが白壁の建造物が連ねている。問屋街として栄え、商品の仲買をして繁盛していたことから仲買町と呼ばれるに至っている。因みに仲買を辞書で引くと次のとおりである【物品や権利の売買の媒介をして営利をはかること:大辞泉】

玉島は、船の航路として多く利用されていたが、柏島と八重の間である現在の唐船もまた急流でありながら船の航路であった。昔、旧暦の11月3日、暴風で吹き荒れ寒々しい中、唐からやってきた船は、日が暮れてないことをいいことに、船を止めようとしなかった。しかし、柏島と八重の海峡を通りかかった唐の船は、暗礁に乗りあがり、暴風を受けて、あっという間に沈没してしまった。これを哀れに思った地元の人々は、祠をたて、唐神様として祀った。これらの出来事より、この地を唐船というようになった。
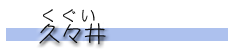
ここは、柏島の北方にあたり、干拓以前は干潟に恵まれていたと推測できる。
『くぐい』とは、渡り鳥である白鳥の古名とされ、この地に白鳥(くぐい)が群棲していたことより、くぐい⇒久々井となったのではなかろうか。
また他説に、柏島には沢山の水源があり、この辺りに9つの井戸があったことから九々井となったとも言われる。この由来となった井戸も現存するという。
===以下編集中===
