
富田の東側に位置し、村中央をかつての玉島往来が通る古い町である。
1068年(治暦4年)の大嘗会の歌に、
遥かにぞいま行末を思ふべきながをの村のながきためしに(藤原経衡)
とある。
推測ではあるが、当時の海岸線(干拓前)を辿ると、長い岬状(尾っぽ状)の地形が多く見られる。これより、長い尾っぽのような地形、が長尾と転移したのではなかろうか。
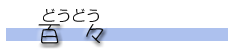
当時海だった頃か、それとも川があったからか・・・。とにかく、百々(どうどう)とは水が流れる音が地名に転移したものである。
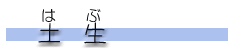
土生とは、急斜面の土地であること。これが地名に転移した。
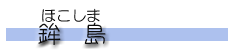
西暦200年頃、仲哀天皇の妻であった神功皇后は、朝鮮新羅へと遠征するために、難波の港(現在の大阪府)から出航し、瀬戸内海を航海して新羅に向かったと言い伝えられる。
この時、当時海に浮いていた鉾島に神功皇后一行は上陸し、鉾(両刃の剣に柄をつけた、刺突のための武器)をたてて兵を募ったと言い伝えられる。これにより鉾島となった。(別説に神功皇后が鉾をたてそのまま忘れていったとの説もあるが、戦いの道具をわざわざ忘れていくだろうか・・。)
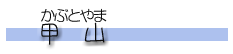
鉾島と同じく、神功皇后が新羅遠征に向かう際、この地で甲を着て、戦いに備えたと言い伝えられる。これにより甲山となった。

正確には大内田新田であるが、現在は作陽大学の東側であり大きな幹線道路が通っている。
この道路が通るまでここには、長尾神社(八幡宮)の秋祭りに奉納する米を作っていた。
この奉納米を作るまでの経緯は、
1068年、後三条天皇が即位する際に行われた大嘗祭において、天皇の儀式に使用される米をこの地で生産したのが始まりである。天皇に献上したのはこの儀式一度きりであるが、この田を普通の田に戻すのは名残惜しいということでそれ以来数百年にわたり、秋祭りに際して長尾八幡宮に献上する田となった。
道路事業でこの数百年にわたる伝統を誇る田が消滅したのは大変残念である。
/font>
