

大嘗祭の和歌集の中に、
天のはらあけて戸島を見渡せば渚静かに波ぞよせくる 藤原家経
とある。これは、歌人藤原家経が、1046年に現在の神崎神社付近から早朝に乙島を見渡して詠んだ歌であるが、乙島の古名は、戸島であったようである。
源平の争乱を書いた、源平盛衰記という文献にはこの付近を『水島の途』とよんでいる。途という字は、戸の漢字を途に当てたもので、戸というのは、源平藤戸の合戦などからもわかるように、海峡をあらわすとされる。『水島途』=『水島戸』がいつしか戸島となったのではないかと思われる。またこれが現在に至るまでに、語呂の悪さからか乙島となった。また、島の形が乙に似ており、かつ乙という字は縁起がよいものでこの字になったとの説もある。

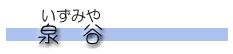
泉谷は、乙島のほぼ中央部に位置し、東、南、西の三方を小高い山に囲まれた狭い谷が北に向かって開いている。
現在の泉谷公会堂の脇に一つの井戸がある。これは古来より四季を問わず噴水する泉であった。また、この泉は、源平水島合戦に陣した数千将兵の給水の源であったといわれている。
この泉がそのまま転移して泉谷となった。

泉谷集落の北側が北泉地区である。古く乙島であった頃は、ちょうど海との境目にあたるだろうと推測される。
ここも泉谷同様、掘れば水が噴出する地であり、上にあげた泉の北側であることから北泉となった。


乙島の西部に位置する渡里。ここは現在でも港に隣接する地区であるが、まだ玉島港に橋がかかっていなかった頃、柏島との間に渡し舟があった。これは数十年前まで行われていたようである。渡し舟の地、が後に転移して渡里となったと推測される。
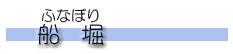
名前のごとくかつては、『船溜り』の地であったのではなかろうかと推測できる。
今では、干拓され、住宅地・商工業地として変貌しつつあるが、少なくとも今から150年前頃までは水島灘が茫漠と広がり、船堀集落の足元まで波が打ち付けていた。
また、当時の海岸線をたどると、弓なり上の入り江を作る。特に冬の北西の強風を防ぐうってつけの地形であったのだろう。
この船溜りが後に転移して船堀となったのであろう。
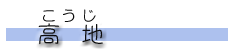
船堀の後背に位置する高地。ここは現在みかんなどの果物の生産が盛んである。一面に広がる畑は、2〜30メートルほどの高さで、高い土地ということがそのまま高地となった。

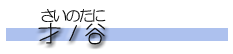
高地を越して、北泉に行く間の谷間が才の谷である。
元は、『塞の谷』 ではなかったのだろうかと推測できる。
昔は、村や集落の出入口、または境に『塞の神』などを祀り、疫病や災難が進入しないように防ぎ護ってもらうという信仰が強かった。
おそらくこの地にも『塞の神』を祀り、安全を祈ったのであろう。
これが後に転移して才の谷になったと思われる。

現在産業道路が貫く場所である。玉島の工業地帯とを結ぶ重要な交通路である。
ここはかつて人口の運河があったのではないかと思われる。
掘貫付近の当時の海岸線をたどってみると、東側に水溜の集落をかかえる山塊と、西側に船堀北部の丘陵との狭間である。
江戸時代の頃であろうか。この狭間を掘り抜いて吉浦や水溜・竹の浦方面の低湿地の悪水排水路を金、また小さな川舟なども通行できるとも考えた水路を通したのではないかと推測出来る。
地元の古老の話によると、現在も水路跡であろうと思われる水門の石柱が人家の残っているというがはっきりとしたことはわからない。
とにかく堀を貫いて水路を通していたことが、後に転移して掘貫になったと思われる。

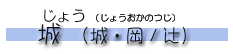
乙島の西側に位置した城は、通常『城・岡ノ辻』と呼ばれ、常照院が置かれている。古くは源平水島合戦の古城があったとされており、『浅口郡誌』によると、六条院村(現浅口市鴨方)にある明王院の末本寺とされ一時廃寺となっていたが、大正期に復興したとされる。
古く古城があったこと、現在でも寺がおかれていることから城とよばれるようになった。

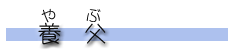
かつては乙島の最南端であったが、現在では沖が干拓され工業地帯が広がる。古く『養父が鼻』とよばれ瀬戸内海有数の景勝地であった。
この地には現在戸島神社がまつられている。創建年代は明らかでないが、古くから鎮座すると言われており、旧名を『養父母大明神』といった。また周辺を養父母山とよんでいたことから、後に、最初の二字をつかい養父と称すようになったと推測できる。
