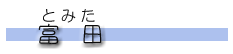
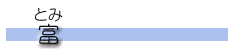
富田は、玉島の北西端に位置する。
富田の中に、付近が海であったころ、漁港として栄えた富地区があり、現在は山深い峠である。漁港として栄えたことに由来し、現在の富の名となっているという。
またこの富は、大嘗会(だいじょうえ)和歌集の中に、
♦村上天皇天慶9年(946)御代 ♦
昔より名づけそめたる富山はわが君が代のためにぞありける
♦後一条天皇長和5年(1016)御代 ♦
富の山風まさりけり君が代は 峰の白雪たゆまふまでに
♦後三条天皇治暦4年(1068)御代 ♦
種わける苗代水をせきあげて 富田の郷にまかせてぞ見る
など、これらの歌は、富に主基田があったことを物語る。後にこれが富田村名の起こりとなった。
中世には、富田庄と呼ばれる荘園が置かれていた地でもある。

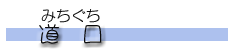
古代瀬戸内海は大和と筑紫とを結ぶ重要な交通路であった。
九州へ派遣される官人、遣唐使、遣新羅使一行も山陽道沿線の津々浦々を伝わって、一ヶ月にも及ぶ、長い旅路を続けたのである。
難波の津を船出して兵庫、室津、牛窓、下津井、草戸(福山)、鞆の浦と通って行くのが普通であるが、大海を通れない小船、また大型の船も風波の荒い時は児島の北側を通り、連島にぬけて甕(もたい)の泊(とまり)(亀山)に避難待ちをしたのであった。
乙島、柏島、七島に囲まれたこの一帯は絶好の避難港であった。ここは道口の津と呼ばれた。
道口の北には富があり、ここは漁村であり、また、矢掛、小田などへ通じる道の入り口となっていた。これにより、道口となったといわれている。

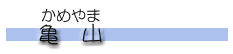
春になると、一面ピンクで染まる丘陵地。桃の生産が盛んで、丘陵地全体が桃などの果樹園である。ここが、古代の港、甕(もたい)の泊(とまり)である。
ここは、鎌倉から室町時代にかけて、大量に甕が生産された地で、窯跡、甕の破片は今でも残る。現在の広島や京都など、遠方の遺跡からもこの地で焼かれた甕が出土しており、大変繁栄していたことが垣間見られる。
また、鎌倉時代の歌人、藤原家隆はこの地で
運び積む もたひの泊舟出して 漕げどもつきせぬ 貢物かな 【大嘗祭】
と詠んでいる。この甕を作る地、甕山が後に転移して亀山となった。
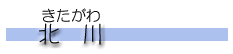
亀山の東に位置する、北川。
この周辺が干拓されて、島地周辺の上竹新田が七島に合併されて、島地が南側、七島が北側に位置した。
北側に七島が位置することから、北側とよばれていたが、これが後に転移して、北川と呼ぶようになった。
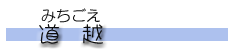
道口より南側あたりが道越である。北側の道口と関連があるように思えるが、ほとんど関連は無いものと考えられている。
道越ももちろんその昔海であった。今は山一面団地となっている山も、海に突き出た半島のような島であった。(ここを現在、陽海山という)ここは、昔、甕海山といい、天正17年(1589)頃、横谷猿掛城に拠った毛利輝元の武将、細川元通が本城である鴨方城の出城として築いたところである。つまり、この地にとりでがあったのである。このとりであった小島と、海を挟んで西側に位置する島との間は、潮の満ち引きにより馬でわたれるほどであったという。この事から道を越えられる=道越となったのではないと思われる。
因みに、陽海山の名の由来は、とりでがあったころ、甕海山の別名を要害山(ようがいざん)と呼ばれていた。これが後に陽(よう)海山(かいざん)となった。

現在の亀山、北川、長尾の一部一帯は八島である。
明治維新当時、富田一帯は、亀山・道口・富・七島・七島のうち島地・上竹新田・道越の七つの村に分かれていたが、廃藩置県以降幾たびか町村の変革が行われ、明治10年2月に七島村と亀山村が合併したことにより七島に亀山を一つたして、八島としたことが由来である。
また別説に、昔壇ノ浦で敗れた平家の落人が、天王山(天王山古墳か?)に集まり、落人狩りに応戦するために、この地で竹を切り、矢を作っていたという。また、この地玉島の海峡で行われた、源平水島合戦の際にも、矢を作っていたという。
これが後に誤伝して
矢島 ⇒ 八島 となったという説もある。

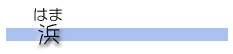
亀山よりも南に位置する浜。ここは平地であり、昔は海であった。
海であった頃、この辺りで塩田が営まれていたという。「浜」という字は塩田をあらわす。この周辺の塩田は、かつて亀山焼の生産のために木々を伐採し、海水を沸かす燃料が乏しかったことからあまり大きな塩田でなかった。
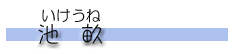
大正期には、牛屋原とよばれていた記録が残る。この辺りには池が点在し、しかも高い所と低い所が平行して連なった地=畝であることから地形がそのまま地名になったと思われる。

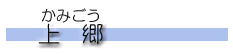
奈良時代の、律令制における地方行政区画は、初め「国・郡・郷」の順であった。この付近は昔、船穂郷であったとの記録が残る。この郷の上方であったことから上郷と名がついたのではなかろうか。

 (道口)
(道口)
道口の中にある大字、札場。
札場とは、昔高札を掲げていた場であったことをあらわす。高札とは、主に江戸時代、法度(はつと)・禁令、犯罪人の罪状などを記し、一般に告示するために町辻や広場などに高く掲げた板の札のことである。廃止されたのは明治六年(1873)当時、この辺りを治めていた庄屋が掲げていた。
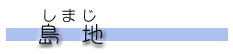
この付近は七つ島が連なっていた。この島のふもとであることから、
島の地 ⇒ 島地 となった。

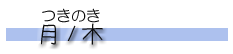
八島の北側の山沿いにあって、昔の浜道である。
古代には数基の古墳が点在していたといわれるが、現在では広域農道、山陽自動車道、家屋となり古墳は破壊されて現存しない。
『月』というのは、ケヤキの木の古名である『槻』が転移したものと推測でき、古くこの地に槻の木、つまりケヤキの木があったのではなかろうか。
