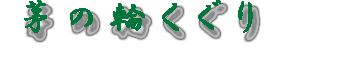
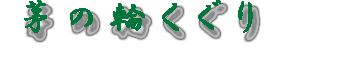
 |
国幣中社の旧社格を持つ安仁(あに)神社の拝殿 の前にチガヤでつくった茅の輪(ちのわ)が立てられています。 毎年7月11日は夏季大祭で茅の輪神事が行なわれます。 参拝した人が茅の輪をくぐり無病息災、厄除けを祈ります。 この由来は、備後風土記逸文の蘇民将来の説話があります。 昔、北海にいますスサノオの神が旅の途中、 一夜の宿を蘇民将来と巨旦将来(コタンショウライ)の兄弟に求めたところ、 弟の巨旦将来は金持ちだったがこれを拒み、兄の蘇民将来は 貧乏であったが快く引き受け厚いもてなしを受けた。 何年か後、神が蘇民将来の家に立ち寄り 後の世に疫病があれば蘇民将来の子孫と云いて茅の輪を腰につけよ と言って去りました。 その後、疫病が流行したとき、蘇民が教えられた通りにすると 蘇民一家は疫病から免れる事が出来たという説話に基づいています。 茅の輪くぐりは正月から6月までの罪穢れを祓う意味で6月から7月に かけて各地の神社で夏越しの祓として行われています。 また、蘇民将来之子孫は疫病除けのまじないになっていて その意味を表す言葉を使った風習が 各地にあります。 |
|---|
11.jpg) |
11.jpg) |
11.jpg) |
|---|---|---|
| 男性神職による舞の奉納 | 人形(ひとがた)白い紙で人の形に切り抜いたもの。自分の氏名、年齢を書きます。 茅の輪くぐりの前に頂きます。 |
|
11.jpg) |
11.jpg) |
11.jpg) |
参拝者は茅の輪くぐりの前に人形に息を吹きかけたり、人形で自分の身体を撫でて、知らず知らずに付いた自分の罪穢れを人形に 移します。 茅の輪は宮司等の先導で左、右、左と3回、蘇民将来と唱えながら茅の輪をくぐります。その間、笛や笙、などの奏楽が流れ、 荘厳に進行します。 |
||
11.jpg) |
11.jpg) |
11.jpg) |
| 最後は人形を拝殿の三方に収めて茅の輪くぐりを終わります。 | 参拝者はチガヤを抜いて持ち帰り悪疫退散、 魔除けとします。 |
|