|
介護保険については、お役人に騙されてはいけません。少なくとも介護の量は確保されても、質は遙かに不足です。世の中、福祉に名を借りた金儲け集団がいっぱい横行しているのです。一部のデイケア医療機関などもそれらの一つです。おのずと質は低下してきます。しかも自己負担額はどんどん増えてゆきます。
例えばご老人の場合医療と介護を同時に受ければ、年金から介護保険料は天引きされるし、介護に要した費用の1割は取られるし、今度将来老人医療も近い将来1割負担になるのですよ。
ご老人の医療費が一月当たり¥1030から¥2000に上がった時に強く反対しなかったからこそ政府は味を占めて¥530を4回の¥2120に、今度は介護の必要なご老人の医療・介護負担を一挙に20倍から50倍に引き上げようとしているのです。政府の対応を見ても、寝たきり老人をかかえる家族の痛みのようなものを感じようとはしていないようです。結局はいずれ医療費の上限などが設定されるでしょうが、あくまでお元気老人だけを対象とした制度で、病気で入院ぎりぎりの在宅患者さんの家族のことなど何にも考えていないのでしょう。これではいずれ療養型病床群がいっぱいになるのではと懸念します。
---36万円の介護と往診など約10万円の医療を受けたとすれば---
1ヶ月あたりの負担は少なく見積もっても(36万+10万)X 0.1 = ¥46000にもなる計算なのです。これに保険では給付されないおむつや食事負担もあるのです。最近の情報によりますと介護は上限3万円、医療は上限3000〜3200円程度になりそうですが、この事例でも少しは安くなるものの33000円以上にはなってしまいます。なんとか医療のみで訪問看護と訪問診察を主体にして安く済ませてあげられないものでしょうか?実際訪問診察などしていますと介護者からはヘルパーなんていらないという希望をよく耳にします。訪問入浴の必要な事例では介護保険やむなしですが、訪問看護で入浴できている事例は多いわけですから、なんとか訪問看護の慢性期の医療適応をも配慮して欲しいものです(おバカな厚生省にはとても期待はできませんが・・・・・・)
在宅サービス:
ランクによっては、要支援の6.15万円から要介護5の35.83万円のサービスを受けられることになっているのですが、今頃になって、厚生省は平均利用額だなどと逃げ口上を唱え始めました。お得意の煙まき説法ですが、実際には少しサービス額は減りそうです。ケアプランというケアマネージャー(介護支援専門員)が以下のサービスを組み合わせる計画を作成するわけですがいろいろ問題が浮上しつつあります。実際厚生省の方針ではヘルパー3回/週、訪問看護1回/週、デイサービス1回/週、などサービスバランスが指定されており、要介護者ニーズとかけ離れていると言わざるを得ない。褥創処置などを5%割引して3級ヘルパーさんにさせようとする案もあり、不安材料の一つである。医学生に手術を頼むようなものと言えば、わかりやすいでしょう。
現在、介護報酬では訪問介護は身体介護、折衷型、家事援助の3タイプに分けていますが、規定通りには進んでいないのは確かです。
また、ショートステイは利用額の利用率の低い方が優先されるなどの信じられないお話が、決定してしまいました。介護保険を目一杯使ってホントに必要な介護をうけているのに、いざショートステイを使う必要が生じたとき、軽い介護度の方が日数など有利な計らいになってしまうのは、おかしいとは思いませんか。
- 訪問介護(ホームヘルパー)、日帰り介護(デイサービス)、ショートステイ、
- 訪問看護、訪問リハビリ、訪問入浴、日帰りリハビリ(デイケア)、
- 痴呆性老人のグループホーム、有料老人ホームの介護、福祉用具の貸与や購入
- 援助、住宅改修費用の支給など
介護施設サービス:
特別養護老人ホーム(32万5000円程度のサービス)
老人保健施設(35万4000円程度)
療養型医療施設(43万1000円程度)
まず訪問し問診を行なう調査員の質が低すぎる。私もケアマネの講習を受けたが、訪問調査員の研修では調査時危ないことはしてはいけないので、立たせてみないで立位保持のチェック項目をチェックし、座らせてもみずに坐位保持をチェックできることになったのは事実です・・・しかも食事中には訪問しなくても嚥下障害を 言われたまま記録できるし・・・ほんとにこんなんで公平が維持できるのか?
立位保持など1秒できれば「できる」になるんですよ。歩行など5メートルを30分かかっても「できる」なんですよ。
ワープロも満足に打てない職員に「一次判定ロジック」への入力を任せているが実際これが信用できるのか。データと出力の違いはチェックできているのでしょうか?担当者はコンピューターのやることだから間違いは無いと言いますが操作するのは所詮人間なのですから。さらに昨年のデータから実際コンピューターの1次判定と認定審査会(2次判定)の結論は既に23.2%もの食い違いが生じている。今年からは、かかりつけ医の意見書も参考にされることになったようだが現在のところ、かかりつけ医よりも的確に病状把握できる人やコンピュータなどはない。(一般的にコンピューターを理解していない人ほどデジタル盲信しているようですが・・・・・)
一次判定ロジックのソフトは今年になって認定基準が甘くなったとの指摘があり早速トラブルの発生が予知されたが、樹型図が公開された今、改めてこのお粗末きわまりない実体が暴露されたのです。調査員が被介護者の知人であった場合など審査に手心を加えることは非常にたやすいことである。審査委員にしても然りである。少なくとも自分の書いた意見書は名前を伏せてあってもわかるので第三者の審査に委ねるべきである。
問診調査には、本来もう少し医療がわかる人間をあてて増員すべきではないのか私の所属するF町では介護認定審査会の医師が自分の書いた意見書を審査するという無茶苦茶な理論も認知している(いまのところなんとか回避されているが)こんな間違いが堂々と横行できるような自治体に介護保険の運用をまかせた県、国の責任はどこにあるのだろうか?
以上の理由から認定審査会がどんなに公平に審査したとしても、訪問調査が不十分であれば6段階(実質5段階)の要援護度選別を公平に行なうのは大変難しいと言わざるを得ない。反対に調査員に能力があれば、記入法如何でで要介護3くらいは簡単に作れてしまうので危険きわまりない制度なのです。
3)厚生省の作った介護度一次判定の欠陥ソフト
一次判定ロジックの問題点について詳しいことは尾形先生のページや土肥徳秀先生のページに詳しく紹介されているので省略しますが、どんたく先生も指摘されていますが、「問題行動」に関する中間評価項目点数というのは大きく分けて「ある」か「ない」の二峰性の分布をするはずですから正規分布からは程遠いし,他の中間評価項目とは明らかに違う性質をもっています。したがって「問題行動点数」を樹形図の枝分かれの判断材料にするのはまさにおろかです。厚生省の三浦とかという統計の知識の欠如した医師・官僚には、中間評価項目追加がいかに馬鹿げているか一刻も早く気づいて欲しいです。こんな馬鹿げたコンピューターロジックを使うくらいなら、医師会が考えた寝たきり度と痴呆度の重回帰分析で判定したほうがよっぽど公平だと感じます。厚生省も自分たちの大間違いにやっと気づきかけてきている---でも、決して認めようとしない。
今年の実際の介護認定に当たり厚生省の示した「介護認定審査会運営要綱」の審査及び判定の手順の項にはっきりとこう書かれています。「日常生活自立度の組合せによる要介護度別分布」や、「要介護度別にみた中間評価項目の平均得点」等を、参考情報として審査判定の際に利用する。また、「要介護認定に対する疑問に答える」の中ではこう答えています。「なお、審査判定の際に、要介護度辺中間評価項目の平均得点、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)や痴呆性老人の日常生活自立度による要介護度の分布を参照することができるようになっていますが、これも要介護度別の平均的な状態像を表現するという点では「状態像の例」と同じ意味を持っていると言ってよいと考えられます。
あれだけ一次判定プログラムに絶対の自信を持っていた厚生省がこうも簡単に、アナログデータである「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」や「痴呆性老人の日常生活自立度」を推奨しなくてはいけない理由が、、、 そうなのです。一次判定プログラムの不備を認識しているのに、厚生省はそれを公にすることなく、あげくの果てに嘘の説明を貫き、このオンボロ一次判定プログラムで我々に要介護度判定をさせようとしているのです。(尾形先生のコメント)
つい最近、厚生省はコンピューターロジックの欠陥を認め、来年度から全く別のソフトの開発に着手することを発表した。もしこれが事実なら、平成12年度はお粗末な欠陥判定で我慢しろということか?
また情報が乏しく不可能なことは認めるが情報収集の手段がアンケートだけというのはいかがなものか。もっと効率良く例えば余って遊んでいる公務員をもっと有効に活用し情報収集させるという方法もある。やっぱりできないものはできないんでしょうか。
確かに客観的という観点が必要だとは思いますが、身寄りのあるなし、介護している人の年齢などは全く無視のデジタル判定である。しかも自治体の公務員はコンピューターよりも頭が硬いはずで・・・・・・・・・・・・・・・
まあ能力のない自治体の能力のない担当者ではもともと絶対無理ではありますが・・・・・・
では具体的に自治体間格差の是正を行なう方法はあるのか。審査委員の質については伝え聞くところによると介護支援専門員よりもお粗末であるそうだ。その教育を徹底する必要があるにもかかわらずただ集まって講習するくらいではまだまだ十分でない。
さらに、業者にとっては、自治体によって介護報酬の原点となる点数の計算法が違うという矛盾もかかえています。例えば同じ業者が同じサービスを行っても、自治体が違うと1点あたりの料金が異なってくるので、利用者が支払う一部負担金も違ってくるのです。ただ自治体境界部に済む住民には理解できないことのようです。
- 医療討議できるような人材は弱小町の地元にはそんなにいるはずがない。
- 現実に私の弱小市町村は、隣の市町村よりもサービスが不足しているばかりか、認定に関わる手法も一段とお粗末です。
したがって医療を必要とする高齢者であるからこそ診断書ばかりでなく主治医の意見書が必要なのです。
ところが実際には公務員やケアマネージャーという全くの素人に身体機能や精神機能までチェックさせようとしている。このチェックすらも適切に行なわれていない。
この制度では介護認定審査会(本来専門職のはずだが実際は医療素人の集まり)の方がたが患者を最もよく理解している家庭医よりも権限を持つことになるのです。仮に認定上のミスや介護中のミスで命にかかわる問題が起こったとして、医師以外のサービス機関でどの程度対応できるのでしょうか?お役所仕事では当然だれも責任をとることはないので、運がなかったと諦めざるを得ない。行政はたぶん主治医の責任にでもするのでしょう。果たしてどこまで「かかりつけ医の意見書」を審査に反影できるか見守ってゆきたい。
上記にも述べたとおり、メンバーは一応、医療福祉分野の専門家ということになっていますが、いくら事前に資料を渡されたとしても、討議5〜6分ではたして十分な審議といえるのだろうか?いまから考えるだけで恐ろしい。
認定審査員は、利用者をランク分けするという責任の重大さを分かっていないはず。なぜなら、裁判と違って書類だけで判断するという欠席裁判なのだから・・・・・
平成10年11月26日の新聞によりますとケアマネージャーの試験の合格者が全国で91,269人岡山県は2,231人とのこと、ここで誤解してはいけないのはこの試験が資格試験でなく実務研修受講資格のための試験であるということです。要するに岡山でケアマネージャーが2231人誕生したのではないということです。
平成11年7月25日のケアマネージャーの試験では岡山県では3300の受験に対し合格は1300余名と合格率40%くらいだそうですが、何れにしても試験内容はというと常識のない3流学校の入試にも劣るもので、こんな人たちの何人に患者さん(要介護者)の生命と介護をまかせられますか?
私も受講試験合格者で実務講習受講終了したケアマネ2期生ですが敢えて提言します。ケアマネージャーはすぐに短大・専門学校卒の資格で国家試験化すべきと考えます。介護をうける人たちは大事なお金の使い方をこの人たちに握られることになるのですから、是非マトモな人であって欲しいと願うばかりです。
合格者を見るといろんな方が合格されているようですが、特に目を引いたのが医師の合格率の低さです。岡山県では、昨年は医師340余名が受験したった220名しか合格できず、今年は99名受験したった66名の医師しか合格できませんでした。しかも講習は平日に行われるので診療所をお休みにしてまで講習を受けて介護支援専門員になるほど暇な医師はいったいどれくらいいるのだろうか(私は暇なのでなれましたが)おそらくは資格だけは取って介護支援事業者の申請に使い金儲けの手段にでもなると考えているのか?実際医師がケアプランを作成することなどないでしょう(絶対ありえません)
ある自治体では、デイサービスを受けているお元気老人に対し、社会福祉協議会の保健婦が介護認定審査を受ける見返りに「もし自立と判定されても、現在のサービスをずっと続けられる」と確約しています。確かに、福祉行政で、今までのサービスを続けることも必要でしょう。しかし、町の税金をある一部の人だけに供するのは如何なものでしょう?あるお年寄りなど現在と同じものと解釈して「1割負担の介護保険より現在の無料のデイサービスを続けられる」とたいそう喜んでいます。これって自治体独自のサービスだとすると、もしかして赤字の特別会計の介護保険の1号保険料が充てられるのでは?そうでなければ一般会計の福祉予算という税金で補填?全くお役人の考えることと言ったら・・・・・・条例で通ってないことを約束するなんて!国以上に自治体はアホですかね。
まあ、不足分を担当者のボーナスで補填するというのでしたら、拍手ものですが。
また、この自治体では、ある常識のないケアマネ医師を抱き込んで、こともあろうに、介護計画策定委員に任じ、保険福祉課長の思うがままに、福祉行政を動かしているという、とんでもない自治体なのです。
一例をご説明しますと、介護計画書によりますと、平成12年度の要介護5の人数より、平成13年度の要介護5の人数が少ない。これを確かめてみると、介護保険が始まると、要介護5の人はどんどんお亡くなりになる。また、要介護4の人はリハビリによってよくなる。したがって要介護5の人は少なくなる。
医師にとって、これは、許されざる発言です。少なくとも減ると分かっていても、同数にするくらいの労りが必要です。まあ、ど素人の役人が、考えたのなら許されるのでしょうが、医師免許を持つ癒着医師が言ったとなると、これは問題です。少なくともこんな無知脳医師を介護計画策定委員に任ずる町、とりわけ町長はとんでもない無能力者と言わざるを得ません。
その結果、必要もない患者さんに、この医師の施設でデイケアを存続させて、丸儲けを企んでいるのは、全くおかしな話なんですが・・・・・・・町がこの不正に手を貸しているなんて。こんな不条理がまかり通るのが、自治体主導の制度なのです。
主治医意見書とかかりつけ医意見書がごっちゃに扱われていますが、ほんとは別物です。ただし一般には同じものと解釈していいでしょう。誤解のないように追記しますが、「かかりつけ医」というのをご存知ですか?これは家庭医や主治医と違って厚生省の企みに気付かぬ日本医師会が騙されて推進した訳の分からぬ制度です。具体的には「かかりつけ医」は患者や受診者が決めるのでなく医療機関が患者の承諾なしに勝手に決めて保険証に記載するものなのです。したがって介護保険では「かかりつけ医意見書」ではなく「主治医意見書」とすべきです。「家庭医」というのは地元に根をおろし、一家でかかりつける開業医のことで、日曜でも夜間でもいつでも診てくれ、なんでも相談にのってくれる総合内科のドクターのことです。したがって病院の勤務医は「主治医」にはなれても「家庭医」にはなれないのです。
例えば外来総合診療という老人のまるめ指導料を算定している医療期間同士が、受診中のご老人に対し自らを勝手に「かかりつけ医」と称し、挙げ句の果てには近隣の競争相手の開業医を受診させぬよう患者さんに脅しをかけるという暴力医療期間が実際にあるのです。これは実例ですが私の医院から100メートルと近いところに居住する患者を10キロほど離れたある病院に紹介したのですが退院しても自分の外来から手放そうとせず、「何十年と家庭医をつとめてきた開業医にかかるなら私の病院では2度と診てやらぬ」なと脅迫したそうで10キロも離れていて、いざというときも往診さえできない医療機関がまさに「かかりつけ医」なんです。
ついでに暴露すると我が医院の近隣にはさらにひどい病院がいくつもあり、骨塩量の測定をたのんだら採血はいうにおよばず、腹部のCTスキャン頭部のCTスキャンに加えMRI-CTや胃腸の内視鏡までされるのです。診療情報提供して検査を依頼してもこのありさまです。いくら医療費があっても足りなくなるのは当然ですよね。
専門員とはいっても、病気のことを知らない人に20〜30万円もの介護費用の使い道をまかせるのです。精神症状や1人暮らし以外の要介護者に在宅でなく入所や入院をすすめるケアマネージャーはたぶん紐付きです。こんなケアマネさんには少なくとも命を預けるのはやめましょう。
自分のお金(介護費用)の使い道と命をまかせるのですから信頼に価する人にお願いしましょう。もちろん自分自身や家族でも計画を立てることは可能ですが、計画書は国保連でなく自治体に提出するので、へたな自治体では現物給付にならず、全額を立て替えるという面倒な方法を採らざるを得ないことになるかもしれません。あなたは取りあえずとは言っても月30万円以上のお金を立て替え払いできますか?いずれにしてもご自分で計画を立てたいならば、かかりつけ医でなくて内科の家庭医に相談されることをお勧めします。
私の医院では、サービス事業は行わず全くボランティア(NPOの設立を考慮中です)でケアプランを作成する予定です。ご自分で計画を立てることも可能ですのでその際にもご相談下さい。現物支給できるように、私は介護支援事業者の申請は行う予定ではありますが------やっぱりやめようかな?
意識障害判定用のJCSを痴呆度の判定に使用しているのは混乱を招くだけですが、そのあたりの事情を認識できないのが自治体の担当者と認定審査会の医師以外の委員なんで困ったことです。委員たちに「意識consciousnessと精神障害mental disturbanceは、本来区別すべきなんだよ。だから訪問調査と医師の意見書では判定が違うんだ。決して医師の判断が間違っているだけではないんだよ」と、子供に話すようにやさしく繰り返し説明しても全く糠に釘状態でした。ところが実はそれ以外にも訪問調査の基準が医療とあまりにもかけ離れたところにあったのです。
まず「寝たきり度」ですが、これは訪問調査では 「能力の有無」を表すものではなく「現在の状態」を表すものだと,審査会テキストには記載されています。(7月下旬の課長会議資料にも全文が記載されています)それでいて「現状でなく、最も頻回に現れる状態」を重視して記載せよというのですから・・・・
一体だれがこんなに訳のわからんことを考えるんでしょうかね?また、医師の意見書と訪問調査の「寝たきり度」や「痴呆度」についてですが、いいかげんな医師の存在(意見のページの悪徳医のような)も確かにありますが、ほとんどのまともな医師たちは、判定に際し、状態の現状でなく、経験からくる知識でついうっかり、先の見通しで行ってしまう傾向にあります。実は私も同じ間違いをおかしてしまいました。でもやっぱり、不安定で近い将来こうなるはずだという判断も差詰め間違いではないようにも思えてしまうものです。
私はケアマネージャーが文句だけを人並み以上にいうだけのコーディネーターになるよりも、ある程度の医療知識を持ち科学的に判断できることが必須だと考えていたのですが、今回ケアマネ講習会に参加してみて、とても無駄なことに思えてきました。確かに人材の確保のため医療、福祉にまったく関係ない分野からの参入者もいることで、もはや介護保険にスーパーバイザーはいなくなったのです。医療分野でさえ「痙性麻痺」と「振戦」の区別の付かない看護婦、保健婦さんもいますし・・・・殆どの方は用語の意味も分かっているのかいないのか?実際講習では、血行不全のしびれも廃用筋力低下も手が首まで上がらない五十肩でも、訪問調査では全部「麻痺」に分類するように洗脳されるのですよ。医者でなければ悩むこともないのでしょうが・・・・・・・
医師としての知識と、プライド(こんなものはなくてもいいのですが)を捨て去ってケアマネ講習を受けている自分が情けない想いです。
このページ作者が推奨する介護保険の認定審査の方法:日本医師会が提唱している「寝たきり度」と「痴呆度」を多重回帰分析して要介護度を判定する方法が、シンプルで、信頼性もあり、自治体の推奨する厚生省のバカどもが作った間抜けた1次判定ロジックよりはずっとましです。
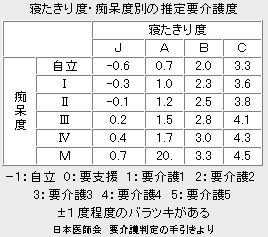
- では、これからの介護保険をどうしたらいいのでしょう?
- 介護保険に関して、私はこう考えます。
とにかく、現制度は不合理、不公平が多すぎます。まずは状態に応じた認定という改善策が急がれます。
今の介護保険は潰して、新介護保険制度として、いちから作り直す。
コンピューター審査に多少のデータの入れ替えで、一次判定が公平になるはずはない。ケアマネージャーは4年制の福祉系の大学卒のみに国家資格にすべき。
少なくとも、介護支援学科とか・・・・作って。それまでの暫定措置は、1次判定をやめて、保健所や公的病院・診療所
の医師の合議体のみで判定を行うべき。(ひも付き防止のため)要支援や要介護1の判定はなくし、、ドイツ方式の軽症、中症、重症の3段階とする。
したがって、デイサービスやデイケアは、介護保険でなく別予算で行う。痴呆と寝たきり度は別々の判定審査とし、重い方を正式採用する。
- さらにいいご意見があれば、メールお待ちします。
前ページへはブラウザの戻るボタンでお戻り下さい