|
1)2次認定手法に中間評価項目を重視した厚生省方式(1次判定99ソフト)による判定を信用するな!厚生省のソフトはロジックがいい加減で、私たち専門家は「おみくじソフト」と呼んでいます。2003.4よりこのおみくじソフトはマイナーチェンジを受けたけれど、またも見事な欠陥ソフトでした。また「要介護状態区分の変更等の際に勘案しない事項について」という一次判定変更禁止条項は二次審査に関して全く意味が無いので即刻廃止すべきである!
2)2次審査はコンピューターロジックの欠陥を審査委員の人力で補正するのが目的とはいえ、どうしても一次判定をたたき台にするなら審査員の勝手な思い込みで判定を下位修正すべきでない!(上位修正はやむを得ないところである)
3)医師の意見書が不備なものは信用するな!(まともな診断書一つ書けない医師には何度同じ依頼をしても無駄である-というのもお粗末な意見書は誰かに注意されない限りは改まりません。困ったことに、かかりつけ医としての自覚のない医師が意見書を書くケースにいい加減なものが多い)しかしながら、この意見書は信用できないとか、この医師は信用できないという決定は審査委員の中の医師がすべきである。まあ医師会の幹部でさえまともな意見書が書けないという事実は、日本医師会自体のリストラが必要では?
4)医師の意見書の実があるものは訪問調査よりも優先させよ!(ちゃんと記載がされていてもチェックを1箇所忘れていたことで信用できないとは絶対言わせないぞ-おまえはミスしたことがないのか?自治体の担当者さん、福祉の専門家さん?)
作者は以下の審査法を提唱します。
1)まず審査会に先駈けて医師としての事前検討(意見書判定):日本医師会が提唱している「寝たきり度」と「痴呆度」を多重回帰分析して要介護度を判定する方法が、シンプルで、信頼性もあり、自治体の推奨する厚生省のバカどもが作った間抜けた1次判定ロジックよりはずっとましなので採用します。
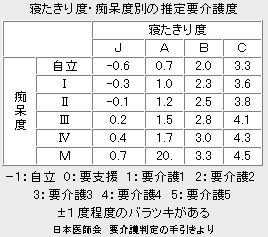
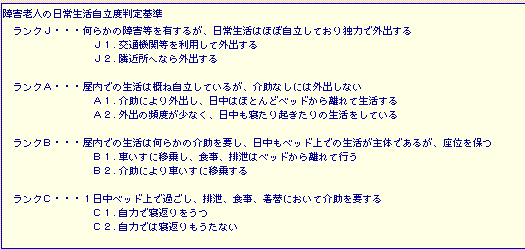
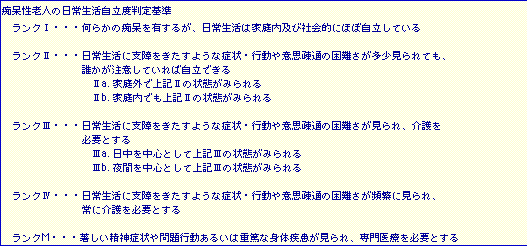
上記の「寝たきり度」と「痴呆度」を多重回帰分析して要介護度を判定する方法を用います。認定審査会は声の大きい人の意見が通ります。脅迫を伴う一種のファシズムです。とにかく大声ではなく脳味噌をもった審査委員を選んで欲しいものです。
意見書の「寝たきり度」や「痴呆度」と訪問調査のそれにはかなりの食い違いが生じます。原因は医師の理解能力不足もありますが、やむを得ないものもあります。その理由は後述します。
これで予習(事前検討)し、大体の要介護度を決定します。コンピューター判定と意見書判定が2段階以上食い違うものでは、訪問調査の特記事項の記載ミスがあれば必ず見つけておきます。これは福祉関係の審査委員をも説得出来るだけの理論武装と予備知識が最低限必要だからです。コンピューター判定の要介護度とほぼ一致するものはそのまま認定されるようにする。
2) 介 護 認 定 審 査 会 で の 合 議 方 針:
非民主的な議長の選出:私の自治体では、民主的な約1名の医師が審査委員のメンバーであるという理由からか?自治体の非民主的ファシズムなのか、医師は議長にも副議長にも議長代行にもなれないことに決められています。従って、民主的手法である合議体委員による互選ではなくして議長が決定されました。そこで医療知識のとんでもない?福祉関係者が勝手に進行をすることになりました。
医師意見書と訪問調査内容の食い違い:両者の内、どちらを参考にすべきかは内容で判断せざるを得ない。文面より医療や福祉の全くお分かりになっていないと思われる記載、症状経過の記載の極端に少ないもの、施設入所の意見書などは全く無視してよい(誤解されぬように追記しますが、ホントに不自由な方も施設では、自分でできることはしているし危ないことなどがないように考えられているので、在宅の状態よりも危険が少ないので軽く判定するように訪問調査員が指導されているためです。)
実際の合議の場:基本的には医師会の2次判定フローチャートにしたがって審査をすすめるのが理想的ですが、個々の審査に入る前にまず訪問調査員の意見から始まるという誠にへんてこな議事進行ですが我慢しましょう。ここではあくまで「自立」「要支援」「要介護1」は非常に似かよった中間評価像をどうするか?で特に審査には注意が払われるべきですが、何分理解能力に欠ける「えせ専門家」の委員たち!まあ判定を下げられないように医師としては努力しましょう。
ちなみに日本の介護保険が大いに参考にしたドイツ方式では、厚生省のアホどものお考えになった7段階の複雑な認定のうち「自立」「要支援」「要介護1」のレベルは想定されておりません。したがって最初から比較的重い3段階の認定(中等度の要介護、重度の要介護、最重度の要介護)を専門講習で資格認定された医師のみが決定できます。そのドイツ方式ですら問題が山積みなのに、あとから行う日本の方がさらにお粗末なのです。日本の最高学府出身の官僚の無知さですね。
日本でも要介護2〜5のみを認定することにしておけば、審査会の悩みも随分減っていたことでしょう。将来、要介護状態に陥るであろう「要支援」というレベルを設定したことが厚生省の大間違いであったことにそろそろ気づいてもいいと思うのは私だけなんでしょうか?デイサービスくらいなら福祉予算で賄うことも考えられるのですから。
結論:以上の理由にもよりますが、私は微力ながら温情とか調査員の雰囲気で実際の2次判定がゆがめられている我が自治体の方針(というか審査委員の質の低さなんでしょうが)に対してあくまで抵抗して行く決意です。もし不服ならばかかりつけ医が県の介護保険審査会に不服申請してあげればいいことではないでしょうか?処分庁さえ作っていない自治体が「まだ不服審査は1件もない」と自慢している自治体なんですから。欠陥コンピューターの1次判定を変えることの意味がハッキリしない以上、2次審査で介護度の変更はしないほうが「公平」の理念に合致していると考えますがいかがでしょう?チャートの形が似ているからと介護度を下げられる立場の方に理由をどう説明できるのでしょうか?少なくとも私には自信はありません。
3)ノートパソコンの持ち込み:
ここからが、他の先生方と違うのですが、私は審査会に審議対象約20〜30例のデーターをノートパソコンに入れて持って行きます。おみくじソフトのエミュレーションソフトなのですが、、まあ手間はかかります。
もちろんデーターが入っていることが事務局に知れると、審査終了後その場で消去しなくてはなりません。あくまでレーダーチャートの状態像を表示するためと説明します。その実は、「ここを増やしてコンピューターに入れてみて下さい」という議長の発言前に判定がわかるので、もし調査項目のチェックを増やすことで介護度が下がるケース(実際これがあるので厚生省ソフトが欠陥ソフトと言われているのですが)では事前に激しく反対し、事務局に対し「私の発言を記録しておくように」確認します。まあ大半は増やしても減らしてもコンピューター審査に変更はないことが殆どでしたが ・・・・
といいますのは、これが不服申請の際、県の介護審査会では、審査会の状況として、大いに参考になるはずで、なまじテープ録音などより効果があります。
実際の審査会では結構この手法は有効でした。無茶苦茶を押し通そうとする委員に対しては、事務局に対し「今の発言は明文化して記録に残しておいてください」というとほとんどのケースはコンピューター通りに判定できます。それだけ委員にも自信はないということでしょうが。誤解のないように追記しますが、この手法はあくまで温情とか調査員の雰囲気で実際の2次判定がゆがめられているケースに限られるべきです。したがって私個人としては訪問調査の内容いかんでは介護度を上げることにやぶさかではありません。
4)最後に:
2次判定は医療福祉の専門家によるはずの認定審査会:実はほとんどは既に訪問調査でことが終了しています。私の属する自治体では訪問調査に関わる調査担当者全員が認定審査会に同席しているという全国的にみても希有な自治体ではありますが、審査ではこれが結構邪魔になります。議長は審査にかかる前にかならず調査員の意見を確認します。このことで比較的容易に雰囲気が変わり、審査委員たちの判定をゆがめるには十分な行為です。審査委員にとっては実際見てもいないケースを判定する権限を持つわけですから責任重大です。治らない難病治療を行う医者のように非常に空しい想いの審査会ですが、関わってしまった限りは医師としてはベストを尽くすべきですが、温情とか雰囲気は審査とは別物であるべきです。
医師の意見書:それにしてもひどい医師意見書が多いのには呆れます。したがって不正確な訪問調査を信用せざるを得ないわけです。まず多いのが記載不足:発病年月日が全部「不詳」ですと。交通事故の後遺症診断書でもあるまいし、1ヶ月か1年か10年かそれ以上かを明確にすべきであるのに。さらには症状経過が「治療中である」「リハビリ中である」「投薬中である」だけで、病名は5つも6つもあるのに、使用中の薬も診療内容も一切記載なし、特記事項も白紙、例え書いてあっても「介護が必要である」とだけ。こんなのならない方がもっとマシ。
審査のあとで事務局に「この先生は若くて油の乗り切った、ケアマネ講習中のはずなのに何でこんな記載しかできないのか?一通¥4000が目的だとすると、患者さんがかわいそうなので、あなたたち事務局から指導をして下さい」「もしどうしてもできないなら医師会の理事にお願いするので医師名を医師会に報告して欲しい」と申し入れしましたが以来なしのつぶて。どうやらこの医師と事務局は特別の関係にあるらしい。
意識障害判定用のJCSを痴呆度の判定に使用しているのは混乱を招くだけですが、そのあたりの事情を認識できないのが自治体の担当者と認定審査会の医師以外の委員なんで困ったことです。委員たちに「意識consciousnessと精神障害mental disturbanceは、本来区別すべきなんだよ。だから訪問調査と医師の意見書では判定が違うんだ。決して医師の判断が間違っているだけではないんだよ」と、子供に話すようにやさしく繰り返し説明しても全く糠に釘状態でした。ところが実はそれ以外にも訪問調査の基準が医療とあまりにもかけ離れたところにあったのです。
まず「寝たきり度」ですが、これは訪問調査では 「能力の有無」を表すものではなく「現在の状態」を表すものだと,審査会テキストには記載されています。(7月下旬の課長会議資料にも全文が記載されています)それでいて「現状でなく、最も頻回に現れる状態」を重視して記載せよというのですから・・・・一体だれがこんなに訳のわからんことを考えるんでしょうかね?
また、医師の意見書と訪問調査の「寝たきり度」や「痴呆度」についてですが、いいかげんな医師の存在(意見のページの悪徳医のような)も確かにありますが、ほとんどのまともな医師たちは、判定に際し、状態の現状でなく、経験からくる知識でついうっかり、先の見通しで行ってしまう傾向にあります。実は私も同じ間違いをおかしてしまいました。でもやっぱり、不安定で近い将来こうなるはずだという判断も差詰め間違いではないようにも思えてしまうものです。
訪問調査自体が不備なことは明白ですが、ケアマネージャーの資質が思ったよりも大事です。私はかつてケアマネージャーが文句だけを人並み以上にいうだけのコーディネーターになりさがるよりも、ある程度の医療知識を持ち科学的に判断できることが必須だと考えてきたのですが、今回ケアマネ講習会に参加してみて、とても無駄なことだということを痛感しました。確かに人材の確保のため医療、福祉にまったく関係ない分野からの参入者もいることで、もはや介護保険にスーパーバイザーはいなくなったのではありますが。医療分野でさえ「痙性麻痺」と「振戦」の区別の付かない看護婦、保健婦さんもいますし・・・・殆どの方は用語の意味も分かっているのかいないのか?実際講習では、血行不全のしびれも廃用筋力低下も手が首まで上がらない五十肩でも、訪問調査では全部「麻痺」に分類するように洗脳されるのですよ。みんな納得して話を聞いているのが怖い。せめて医学書で講義するヘルパーさんの方がまともだったりして・・・・・
こんなことは、医者でなければ悩むこともないのでしょうが・・・・・・・
[上手な介護保険の利用法][介護保険をよく知ろう][ケアマネージャーとは] [これでいいのか介護保険][介護保険ここだけの話][どんたくのコーナー][医学一般講座][医療制度の変遷] 前ページへはブラウザの戻るボタンを押してください